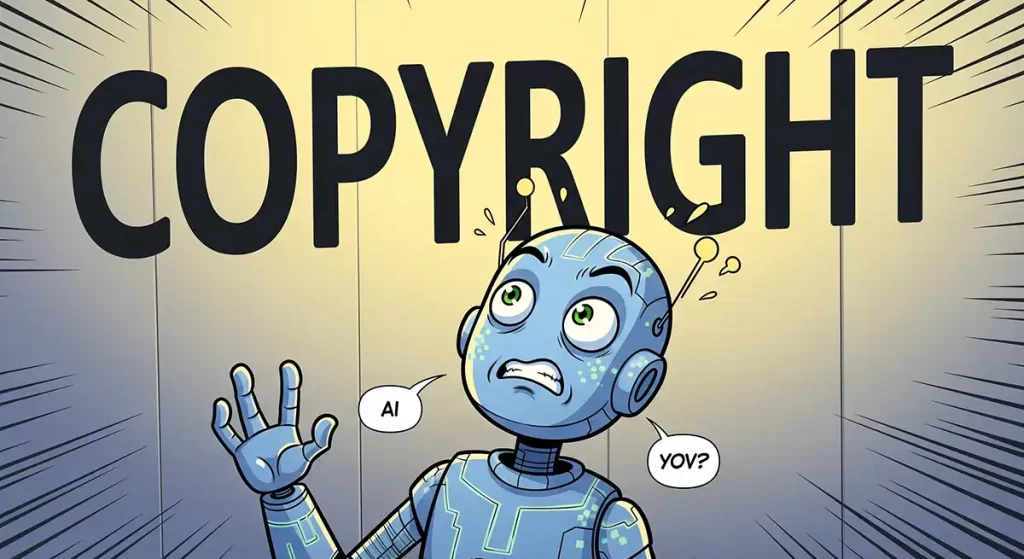
「AIで画像を作ったけど、これって自由に使えるの?」「SNSに投稿したり、ブログに使ったりしても大丈夫?」
AI生成画像の活用が広がるにつれて、多くの人が気になるのが「著作権」や「利用ルール」についてではないでしょうか。せっかくAIが素晴らしい画像を生成してくれても、ルールを知らずに利用して、後でトラブルになってしまうのは避けたいですよね。
このページでは、AI生成画像に関する著作権と利用ルールについて、超初心者さんにも分かりやすく解説していきます。「これだけは知っておこう!」というポイントに絞って、安心してAI画像を利用するための知識をお届けします。
\ AIスキルを短期間で伸ばしたい方へ /
ChatGPT・動画生成AI・画像AIを体系的に学べる講座。初心者でも安心のサポート付きで、最短10日で実務レベルに到達できます。
バイテック無料カウンセリングを見る1. AI生成画像に「著作権」は発生するの?
まず、最も気になるのが「AI生成画像に著作権は発生するのか?」という点です。現在の日本の著作権法の考え方では、少し複雑な状況にあります。
1-1. 原則として「人間の創作物」に著作権が与えられる
日本の著作権法は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を「著作物」と定義し、その著作物を創作した「著作者」に著作権を与えています (1)。
ここで重要なのは、「人間の創作的な活動」によって生まれたもの、という点です。AIは、あくまでプログラムであり、自らの意思や感情を持って創作活動を行うわけではありません。そのため、AIが単独で生成した画像そのものには、原則として著作権は発生しない、と解釈されることが多いです。
1-2. 人間が「創作性」を加えた場合は著作権が発生する可能性
ただし、AIが生成した画像を、人間がさらに加工したり、編集したり、複数のAI生成画像を組み合わせて新たな作品を作り出したりして、そこに人間の「創作性」が加わったと認められる場合は、その「人間の創作性」の部分に著作権が発生する可能性があります。
- 例:
- AIが生成した画像の不自然な部分を修正し、色合いや構図を大幅に調整した。
- 複数のAI生成画像を組み合わせ、独自のストーリー性やテーマを持たせた。
- AIが生成した画像を元に、手描きで加筆修正し、新たなイラストとして完成させた。
このように、AIはあくまで「ツール」であり、そのツールを使って人間がどれだけ創造的な工夫をしたかが、著作権発生の判断基準となります。
2. AI生成画像の「利用ルール」:ツールごとの規約が重要!
AI生成画像の著作権の解釈はまだ発展途上ですが、実際にAI画像を利用する上で最も重要なのが、あなたが利用しているAI画像生成ツールの「利用規約」です。
2-1. 各AI画像生成ツールの利用規約を必ず確認する
AI画像生成ツールは、それぞれ異なる利用ルールを定めています。特に以下の点を確認しましょう。
- 商用利用の可否: 生成した画像を、ブログの収益化、商品デザイン、広告など、ビジネス目的で利用できるか。
- 著作権の帰属: 生成された画像の著作権が、AIツールの提供元にあるのか、それとも画像を生成したユーザーにあるのか。
- クレジット表記の必要性: 画像を利用する際に、AIツール名や提供元のクレジット表記が必要か。
- 禁止事項: どのような画像の生成や利用が禁止されているか(例:特定の人物の顔を生成する、差別的な内容、過激な内容など)。
- 学習データへの利用: あなたが生成した画像が、AIのさらなる学習データとして利用されるか。
例:
- Canva: 無料プランで生成した画像は、Canvaのサービス内で作成したデザインの一部としてSNSやブログで利用できますが、画像単体での販売など、一部制限がある場合があります (2)。
- Bing Image Creator: 個人利用は可能ですが、商用利用には制限がある場合があります。また、Microsoftの「コンテンツポリシー」に準拠する必要があります (3)。
- Midjourney / Stable Diffusion: 有料プランでは商用利用が許可されていることが多いですが、それぞれのライセンス体系や利用規約を詳細に確認する必要があります。
AI画像を利用する際は、必ず公式サイトで最新の利用規約を確認し、それに従うようにしましょう。
2-2. 学習データの著作権侵害リスク
AI画像生成ツールは、大量の既存の画像を学習データとして利用しています。そのため、AIが生成した画像が、偶然にも既存の著作物(イラスト、写真、キャラクターなど)に酷似してしまうリスクがゼロではありません。
- 対処法:
- 生成された画像が、特定の既存の作品に酷似していないか、自分の目で確認しましょう。
- もし酷似していると感じた場合は、その画像の利用を避け、再生成するか、別のデザインを検討しましょう。
- 特に、有名なキャラクターやブランドロゴなど、著作権で保護されているものと酷似するAI生成画像は、著作権侵害のリスクが高いため、利用を避けるべきです。
3. AI画像を安全に利用するためのチェックリスト

AI生成画像を安心して利用するために、以下のチェックリストを活用しましょう。
- 利用するAIツールの利用規約を読みましたか? (商用利用の可否、クレジット表記の有無、禁止事項などを確認)
- 生成された画像は、既存の著作物に酷似していませんか? (特に有名なキャラクターやブランドなど)
- 画像の内容は、公序良俗に反していませんか? (差別的、暴力的、性的な内容など)
- 画像は、個人情報やプライバシーを侵害していませんか? (特定の個人の顔や個人を特定できる情報など)
- 画像を加工・編集した場合、その部分にあなたの創作性が加わっていますか? (もし著作権を主張したい場合)
- ブログやSNSに利用する場合、適切な代替テキスト(alt属性)を設定していますか? (SEO対策やアクセシビリティのため)
4. AI生成画像の未来と著作権の議論
AI生成画像に関する著作権や利用ルールは、まだ発展途上の分野であり、世界中で議論が続けられています。法整備も追いついていない部分が多く、今後、新たな判例や法改正によって解釈が変わる可能性もあります。
- 透明性の向上: AIがどのようなデータを学習し、どのように画像を生成したのか、そのプロセスをより透明化する動きも出てきています。
- ウォーターマークやメタデータ: AI生成画像であることを示すウォーターマーク(透かし)や、メタデータ(画像の付帯情報)を付与する技術も開発されています。
- 新たなライセンスモデル: AI生成画像に特化した新たなライセンスモデルも検討されています。
私たちは、これらの動向に注目しつつ、常に最新の情報を得るように心がける必要があります。
5. AI生成画像を賢く、安心して利用しよう!
AI生成画像は、私たちのクリエイティブな活動を大きくサポートしてくれる強力なツールです。しかし、その力を最大限に活用するためには、著作権や利用ルールに関する正しい知識を持つことが不可欠です。
このページで解説した「これだけは知っておこう!」というポイントを参考に、AI生成画像を賢く、そして安心して利用してください。ルールを守り、モラルを持って活用することで、AIはあなたの素晴らしいパートナーとなってくれるでしょう!
関連記事
- 第1回:AIってなぁに?わたしたちの暮らしとAIの意外な関係
- 第2回:生成AIって何?絵を描いたり、文章を書いたりできるAIのふしぎ
- 第16回:絵が描けなくても大丈夫!画像生成AIってどんなもの?
- 第17回:Canvaで簡単AI画像生成!無料で始めるデザイン体験
参考情報
- 公益社団法人著作権情報センター:AIと著作権
- Canvaヘルプセンター:Canvaのコンテンツライセンス契約
- 文化庁:生成AIと著作権について
- 内閣府:生成AIと著作権
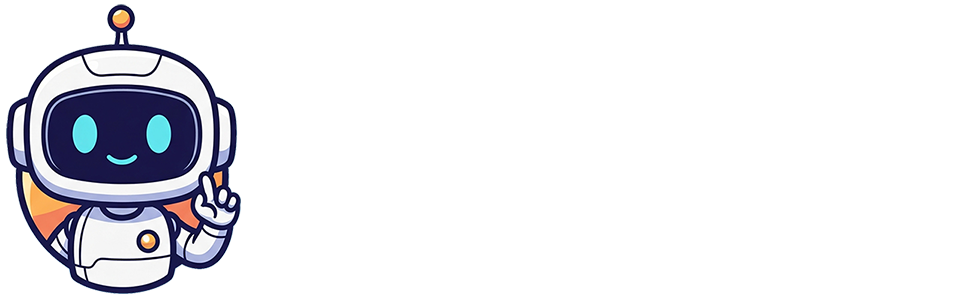
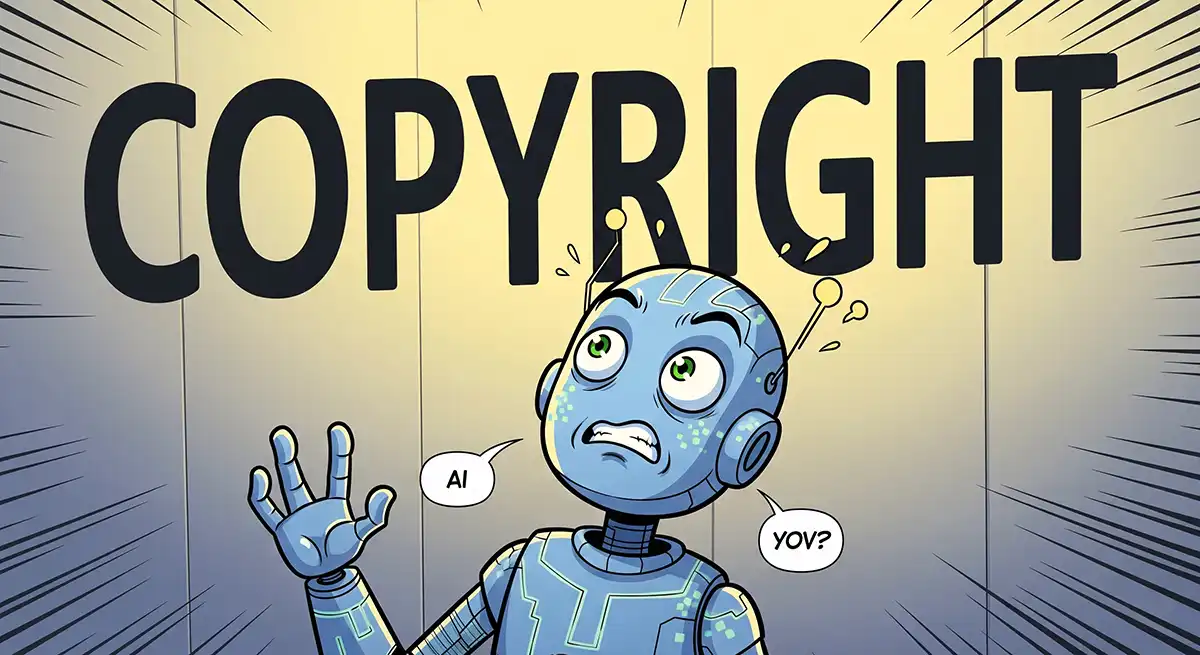


コメント