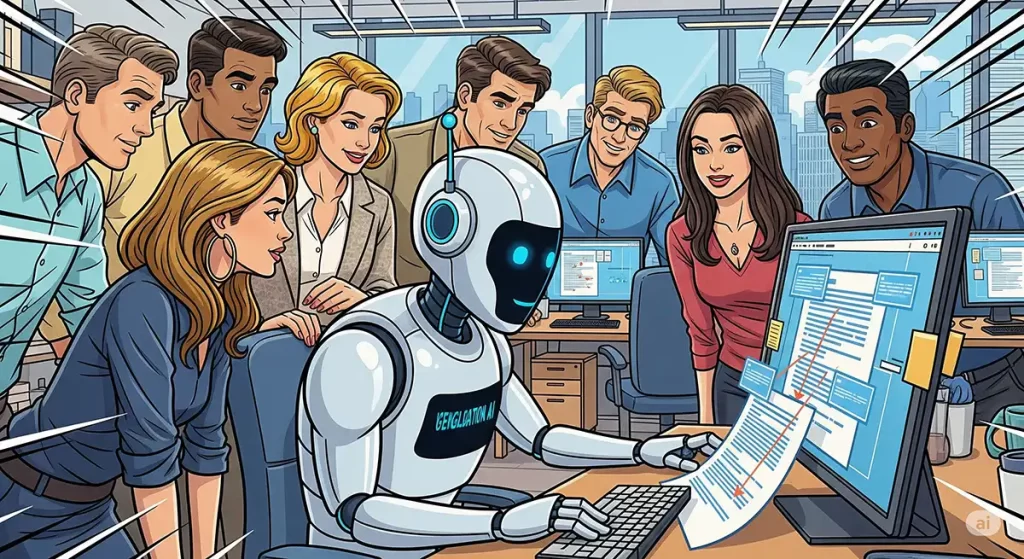
近年、生成AIによる文章作成が急速に普及し、便利さの一方で「この文章は本当に人間が書いたのか?」という不安も増えています。特にブログ運営者やライター、教育関係者にとっては、AI生成コンテンツの判別は品質や信頼性を守るために重要です。そこで必要になるのが「生成AIチェッカー」なのです。しかし、生成AIチェッカーは数多く存在し、精度や日本語対応に差があります。
本記事では、初心者でも迷わず選べるよう、厳選したおすすめの生成AIチェッカーを比較表付きで紹介します。
この記事を読むことで自分に最適な判定ツールを見つけ、安心してAIと共存できる環境を整えられるでしょう。
\ AIスキルを短期間で伸ばしたい方へ /
ChatGPT・動画生成AI・画像AIを体系的に学べる講座。初心者でも安心のサポート付きで、最短10日で実務レベルに到達できます。
バイテック無料カウンセリングを見るh2: 生成AIチェッカーとは?
生成AIチェッカーは、文章を解析してAIが作成した可能性を判定するツールです。
判定には「単語の多様性(バースト性)」や「予測困難性(困惑度)」といった自然言語処理技術が使われます。
主な用途
- 学校でのレポートや論文のオリジナリティ確認
- メディアや企業ブログでのAI生成記事チェック
- クライアント納品物の品質管理
各ツール詳細レビュー(公式リンク付き)
| ツール名 | 日本語対応 | 精度(目安) | 無料プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| GPTZero | △ | 高(英語優位) | ○ | 教育機関採用多数 |
| Originality.AI | △ | 非常に高 | × | コピペチェック統合 |
| Copyleaks | ○ | 高 | ○ | 教育機関利用実績豊富 |
| Sapling AI Detector | △ | 中 | ○ | ビジネス文書向け |
| Writer.com | △ | 中〜高 | ○ | チーム利用可能 |
| Content at Scale | ○ | 高 | ○ | SEO特化型 |
| ZeroGPT | ○ | 中 | ○ | シンプルで高速 |
GPTZero
GPTZeroは、生成AIが作成した文章を検出するAIチェッカーです。GPTZeroは、AIの文章生成方法のバースト性(Burstiness)とパープレキシティ(Perplexity)という2つの指標を基に、AIが書いたかどうかを判定します。
- 特徴:バースト性(Burstiness)とパープレキシティ(Perplexity)
- バースト性とは、文章の単語や文の長さのばらつきを測る指標です。人間が書いた文章は、短い文と長い文が混在するため、バースト性が高いとされます。
- パープレキシティとは、文章がどれだけ予測可能かを測る指標で、テキストの複雑さを示します。AIが生成した文章は、統計的に確率の高い単語を選ぶ傾向があるため、人間が書いた文章よりもパープレキシティが低くなります。
GPTZeroはこれらの指標を分析することで、AIが書いた文章に特有のパターンを識別し、人間が書いた文章と区別します。これにより、教育や研究分野での不正行為防止に役立ちます。また、APIも提供されており、外部システムとの連携も可能です。
- 日本語対応:部分的(英語が得意)
- 料金:無料プランあり(回数制限)、有料は月額制
- 公式サイト:https://gptzero.me
Originality.AI
Originality.AIは、AI生成コンテンツの検出に特化した有料ツールです。AIコンテンツの検出だけでなく、盗作(剽窃)チェック機能も備えているのが大きな特徴です。特にコンテンツ制作者、編集者、教育関係者などを主要なターゲットとしています。
- 特徴:プロ向け。AI検出+盗用チェックが1度に可能。
- 高い検出精度: ChatGPTやGPT-4、Claudeなどの主要な大規模言語モデル(LLM)で生成されたコンテンツを高い精度で検出すると謳っています。
- 多機能: AI検出と盗作チェックを一つのツールでまとめて行える点が強みです。これにより、コンテンツのオリジナリティと品質を同時に確認できます。また、ウェブサイト全体のAIコンテンツ監査機能も備えています。
- 有料サービス: GPTZeroとは異なり、無料プランはなく、クレジットを購入する従量課金制となっています。これは、個人利用よりも企業やプロフェッショナルな利用に適していることを示唆しています。
- Chrome拡張機能: ブラウザに拡張機能を追加することで、ウェブページ上でAIコンテンツのチェックを簡単に行うことができます。
Originality.AIは、コンテンツの信頼性を確保したいプロフェッショナルにとって非常に有用なツールですが、有料であるため、使用目的や頻度を考慮して導入を検討する必要があります。
- 日本語対応:△
- 料金:有料のみ($0.01/ワード)
- 公式サイト:https://originality.ai
Copyleaks
Copyleaksは、AIが生成したテキストだけでなく、盗作(剽窃)も検出する総合的なコンテンツ検証プラットフォームです。特に、教育機関や企業、コンテンツ制作者の間で広く利用されています。
- 特徴:盗用チェックとAI判定の両方が高精度。
- 高い検出精度: GPT-4、Gemini、Claudeなど、さまざまな大規模言語モデル(LLM)に対応しており、99%以上の精度を謳っています。また、言い換えられた文章や文字操作など、巧妙な手口にも対応しています。
- 多機能性: AI検出と盗作チェックを同時に行えるだけでなく、ソースコードの盗作検出や、30以上の言語でのAI検出、100以上の言語での盗作検出に対応しています。
- 多様な利用シーン: GoogleドキュメントやMoodle、Canvasといった学習管理システム(LMS)との連携機能も提供しており、教育現場での利用に適しています。また、ブラウザ拡張機能を使えば、ウェブページ上のテキストを簡単にチェックできます。
- AI Insights: テキストがなぜAIによって生成されたと判断されたのか、その理由を分析・可視化する独自の機能も提供しています。
Copyleaksは、コンテンツの信頼性を確保したいプロフェッショナルにとって、非常に包括的なソリューションと言えます。
- 日本語対応:○
- 料金:無料プランあり
- 公式サイト:https://copyleaks.com
Sapling AI Detector
Sapling AI Detectorは、文章の校正ツール「Sapling」に組み込まれているAI検出機能です。GPTZeroと同様に、文章のパープレキシティ(Perplexity)を分析して、AIが生成したテキストかどうかを判定します。
- 特徴:ビジネス文章に特化。簡単操作。
- 高い検出精度: ChatGPT、GPT-4、Claude、Bardなどの主要な大規模言語モデルで生成されたテキストを高い精度で検出すると謳っています。特に、学術論文やビジネス文書など、専門的な文章の検出に強みを持っています。
- パープレキシティの分析: 文章の複雑性を示すパープレキシティのスコアに基づいて、AIが作成した確率をパーセンテージで表示します。スコアが高いほど人間が書いた可能性が高く、低いほどAIが書いた可能性が高いと判断されます。
- 無料利用が可能: 基本的なAI検出機能は無料で利用でき、ChromeやGoogleドキュメントの拡張機能としても提供されています。これにより、日常的な執筆や編集作業の中で手軽にチェックできます。
- 校正機能との連携: Saplingはもともと文法やスペル、トーンを改善する校正ツールであるため、AI検出と併せて文章の品質向上に役立ちます。
Sapling AI Detectorは、文章の校正作業とAI検出を同時に行いたいユーザーにとって、非常に便利なツールです。個人利用や教育現場での利用に適しています。
- 日本語対応:△
- 料金:無料プランあり
- 公式サイト:https://sapling.ai/ai-content-detector
Writer.com AI Content Detector
Writer.com AI Content Detectorは、文章校正ツール「Writer」に統合されたAIコンテンツ検出機能です。GPTZeroやSaplingと同様に、テキストの予測可能性を基に、人間が書いたかAIが書いたかを判定します。
- 特徴:チームでの共同作業に便利。
- 高い検出精度: ChatGPTやGPT-4、Claudeなどの大規模言語モデル(LLM)で生成されたコンテンツを高精度で検出します。特に、マーケティングやビジネスライティングに特化しており、専門的な文章の検出に強みを持っています。
- パーセンテージでの確率表示: テキストがAIによって生成された確率をパーセンテージで表示します。このスコアは、文章のパターン、構造、単語の選択など、複数の要素に基づいて算出されます。
- 有料プランの一部: この機能は、主にWriterの有料プランに組み込まれており、無料版では機能が制限される場合があります。企業やチームでのコンテンツ作成プロセスを効率化するために設計されています。
- 校正・文法チェック機能との連携: AI検出機能だけでなく、文法やスペルチェック、トーン調整など、Writerが提供する他の校正ツールとシームレスに連携します。これにより、コンテンツの品質を総合的に向上させることができます。
Writer.comは、企業のブログ、マーケティング資料、技術文書など、プロフェッショナルなコンテンツを作成するチームにとって、AIコンテンツの信頼性を確保するための強力なツールです。
- 日本語対応:△
- 料金:無料あり
- 公式サイト:https://writer.com/ai-content-detector/
Content at Scale
Content at Scaleは、AIによる記事生成プラットフォームであり、そのツール群の一つとしてAIコンテンツ検出ツールを提供しています。この検出ツールは、主に自社で生成した記事がAIコンテンツと見なされないようにするために開発されましたが、一般にも無料で公開されています。
- 特徴:SEO記事作成サービス付属の判定機能。
- 高い信頼性: このツールは、GoogleがAIコンテンツをどのように評価しているかという視点を強く意識して開発されました。そのため、Googleの検索エンジンがAIコンテンツを検出する可能性のある文章のパターンを分析し、人間が書いたかのような自然な文章を評価することに特化しています。
- シンプルなインターフェース: 検出ツールは非常にシンプルで、テキストをボックスに貼り付けてボタンを押すだけで、AIによる生成確率が0%から100%の間でパーセンテージで表示されます。
- AI生成コンテンツの最適化: AIコンテンツの検出だけでなく、コンテンツを「人間らしい文章」に最適化するためのヒントを提供することを目指しています。これは、AIで記事を量産するユーザーが、検索エンジンに評価されるコンテンツを作成できるようにするためです。
- 無料利用: 誰でも無料で利用できるため、AIで作成したコンテンツがGoogleのペナルティを受けないか確認したいユーザーにとって便利です。
Content at Scaleの検出ツールは、特にSEOを重視するWebライターやコンテンツマーケターにとって、AI生成コンテンツの品質をチェックする上で役立ちます。
- 日本語対応:○
- 料金:無料版あり
- 公式サイト:https://contentatscale.ai/ai-content-detector/
ZeroGPT
ZeroGPTは、AIが生成したテキストを検出するために広く利用されている無料のオンラインツールです。その主な特徴は、シンプルで使いやすいインターフェースと、AIが書いた可能性のある文章を色分けして表示する機能です。
- 特徴:無料・シンプル・高速。
- 直感的なUI: 検出したいテキストをボックスに貼り付けて「Detect Text」ボタンを押すだけで、すぐに結果が表示されます。難しい設定や操作は必要ありません。
- AI生成部分の色分け表示: 検出結果は、AIが生成したと判断された部分が黄色やオレンジ色にハイライトされます。これにより、文章のどの部分がAIによって書かれた可能性が高いのかを一目で把握できます。
- AI生成確率の表示: テキスト全体がAIによって生成された確率をパーセンテージで表示します。このスコアは、文章の複雑さやパターンなどに基づいて計算されます。
- 無料利用: ほとんどの機能が無料で提供されており、手軽にAIコンテンツをチェックしたいユーザーにとって非常に便利です。有料プランも存在しますが、基本的な検出機能は無料版で十分利用できます。
ZeroGPTは、学生やWebライター、教育関係者など、AI生成コンテンツの信頼性を素早く確認したいユーザーに特に適しています。シンプルさとわかりやすさが最大の魅力です。
- 日本語対応:○
- 料金:無料
- 公式サイト:https://www.zerogpt.com
生成AIチェッカーの精度と信頼性の目安
生成AIチェッカーは、文章がAIによって作られた可能性を判定する便利なツールですが、その精度や信頼性にはいくつかの注意点があります。
① 完全に正確ではない
生成AIチェッカーの精度と信頼性は、完璧ではありません。その理由は、AI技術が急速に進化し、人間と区別がつかないほど自然な文章を生成するようになったためです。
多くのAIチェッカーは、文章のパターンや単語の選択の偏りを分析していますが、AIがこれらのパターンを「学習」して回避するようになると、検出が困難になります。例えば、AIは単語のパープレキシティやバースト性を調整することで、人間らしい文章を模倣できます。
そのため、AIチェッカーの結果はあくまで「目安」として利用すべきです。AIが生成したと判定されても実際は人間が書いた可能性があり、逆に人間が書いたと判定されてもAIが書いた可能性もあります。最終的な判断は、複数のツールを試したり、自身の目で内容を精査したりすることが重要です。
- 誤判定の可能性:人間が書いた文章をAI扱いしたり、逆にAI生成文を人間扱いすることもあります。
- 文章の長さや構造に左右される:長文になるほど、ツールの判定は安定しやすくなります。
② ツールによって精度が異なる
AIチェッカーツールの精度は、ツールごとに大きく異なります。その背景には、各ツールが採用しているAI検出技術の違いがあります。
例えば、GPTZeroやSaplingは「バースト性」や「パープレキシティ」といった文章の統計的特性を重視しますが、Content at ScaleはGoogleのアルゴリズムを意識した独自の方法を採用しています。また、Originality.AIやCopyleaksは、盗作チェック機能も統合することで、より包括的なコンテンツ分析を行っています。
新しいAIモデル(例:GPT-4o、Gemini 1.5 Pro)が発表されるたびに、これらのモデルに対応するためにツールのアルゴリズムも更新される必要がありますが、その対応速度も各ツールによって差があります。そのため、特定のAIチェッカーで「人間が書いた」と判定されても、別のチェッカーでは「AIが書いた」と判定されることがあり、ツールの選択によって結果が変わることを理解しておく必要があります。
- 高精度系:AIの特徴的な文体やリズムを分析するため、判定は比較的信頼できる
- 無料系:ライトユーザー向けで手軽ですが、判定はあくまで参考程度
③ 判定結果はあくまで“目安”
生成AIチェッカーの判定結果は、あくまで目安にしかなりません。
その主な理由は、AIチェッカーが完璧ではないからです。AIチェッカーは、文章のパターンや単語の選択の偏りなど、特定の「AIらしさ」を検出するアルゴリズムに基づいています。しかし、AI技術は日々進化しており、人間が書いた文章に限りなく近い、巧妙な文章を生成できるようになっています。
例えば、AIが「バースト性」や「パープレキシティ」といった指標を調整して、人間らしい文章を模倣することも可能です。そのため、AIが生成したテキストが「人間が書いた」と誤判定されたり、逆に人間が書いた文章が「AIが書いた」と誤判定されたりすることがあります。
これらのツールはコンテンツの信頼性をチェックする上で有用ですが、一つの結果だけで判断するのではなく、複数のツールを試したり、自身の目で内容を精査したりすることが重要です。
- 一つのツールの結果だけで判断せず、複数ツールでクロスチェックするのが安全
- 重要な文章や公開予定の文章は、人間の目でリライト・校正して精度を補完する
| チェッカーの種類 | 信頼性 / 精度の目安 |
|---|---|
| 高精度系(有料・学術系) | ★★★★☆(高い) |
| 無料系(ライトユーザー向け) | ★★☆☆☆(参考程度) |
| 複数ツール併用 | ★★★★★(安定的) |
④ AI+人間の併用がベスト
AIチェッカーを最大限に活用するには、「AIと人間の併用」がベストなアプローチです。
AIチェッカーは、大量のテキストを素早く分析し、AIが生成した可能性のある部分を効率的に見つけ出す強力なツールです。これにより、人力では見落としがちな文章の偏りや不自然な点を特定できます。
しかし、AIチェッカーの判定は完璧ではありません。前述の通り、誤判定の可能性も考慮する必要があります。そこで、チェッカーの判定結果を参考にしながら、最終的な判断を人間が行うことが重要です。
具体的には、チェッカーがAI生成と疑わしいと判断した部分を、人間が目で見て、文脈や論理性を再確認します。これにより、AIチェッカーの効率性と、人間の洞察力や判断力を組み合わせ、コンテンツの信頼性を高めることができます。
- AI生成文章の分析・要点抽出
- 人間による体験談や考察の追加
こうした組み合わせで、チェッカーのスコアに頼りすぎず、文章の信頼性・独自性を高められます。
生成AIチェッカー活用のコツ(実務で使える10のポイント)
① 2〜3ツールでクロスチェックする
1つの結果に依存せず、性質の異なるツールを併用しましょう(例:高精度系+無料系)。判定が割れたら「要再確認」の合図。特に重要原稿は最低2回チェックを推奨。
② 長文は“かたまり”に分けて判定する
1本まるごとより、見出し単位・300〜600文字で分割すると精度が安定。AIっぽい箇所(導入の定型文/結論の常套句など)がピンポイントで分かるので、修正もしやすいです。
③ 下書き→編集後で2回測る(差分で判断)
草稿段階と仕上げ段階の2タイミングで判定。スコアが下がらない=改善不足のサイン。どの修正が効いたかを学習でき、次回以降の執筆が洗練されます。
④ 自分の“合格ライン”を作る(キャリブレーション)
ツールごとに指標やスコアの癖が違います。人間が書いた既存記事10〜20本でテストし、平均的なスコア帯を把握して自社の基準値(例:「このツールでAI率X%未満」)を決めましょう。
⑤ 人間らしさを足すリライト手順(ミニチェックリスト)
AIっぽさは抽象・一般論・均一リズムに出ます。以下を加筆・調整するとAI率が下がりやすいです。
- 一次情報:自分の体験・数値・失敗談・現場の写真メモ
- 固有名詞:製品名/地名/日付/具体数値(根拠も一言)
- 文体の変化:短文↔長文、箇条書き、具体→抽象の往復
- 反証/例外:敢えて弱点や代替案も書く
- 口調のむら:接続詞の単調さ(「まず」「次に」連発)を崩す
⑥ プロンプト段階で“AIっぽさ”を抑える
生成AIに頼る際は、最初から人間味が出る指示を。
- 「一次情報の挿入ポイントを{●●の体験}として空欄で残して」
- 「具体例を3つ。出典or条件も併記」
- 「語尾・文長をランダム化。比喩/弱点/反論も1つずつ」
→ こうして出した素案に自分の経験で肉付けし、再チェック。
⑦ 機密・個人情報は“加工してから”アップロード
外部ツールに本文をそのまま貼らず、固有名詞や数値をダミーに置換(例:会社名→【A社】、売上→【XX万円】)。どうしても原文を出せない場合は、要所のみ抜粋して判定。
⑧ ワークフローに組み込む(SOP化)
書く → 自己校正 → チェッカーA → 修正 → チェッカーB → 記録 → 公開の順で固定。
記録はスプレッドシートでOK:
- 列例:URL / 日付 / 文字数 / 使用ツール / スコア / 対応(修正内容) / 判定者
継続するとどの修正が効くかがデータで見えます。
⑨ 教育・審査用途は“運用ルール”を明文化
誤判定はゼロではありません。複数ツール確認+本人ヒアリングを基本に。引用や定型文(注意書き・規約)、コードや式は誤判定しやすいのでチェック対象から外すルールを。
⑩ 多言語・特殊文書の注意
- 日本語+英語混在は言語ごとに分けて判定。
- 詩/キャッチコピー/テンプレは特徴的で、AI扱いされやすい。背景説明を追記して“人間の意図”を可視化しておくと誤判定対策になります。
生成AIチェッカー FAQ
- Q無料で使える生成AIチェッカーはありますか?
- A
はい。ZeroGPTやCopyleaksなど、無料版を提供しているツールがあります。
- Q日本語文章でも正確に判定できますか?
- A
ツールによります。CopyleaksやContent at Scaleは比較的日本語精度が高いです。
- Q判定結果は100%正しいですか?
- A
いいえ。参考情報として利用し、最終判断は人間が行うのが望ましいです。
まとめ
生成AIの文章は便利ですが、品質や信頼性を保つためには「AI生成かどうか」を判定できるツールが欠かせません。
本記事では、初心者にもわかりやすく、無料から有料までおすすめの生成AIチェッカーを比較・解説しました。判定精度や日本語対応状況、使いやすさなどを踏まえ、自分の目的に合ったツールを選べば、コンテンツの信頼性向上や著作権リスク回避に役立ちます。記事内の比較表やリンクを活用し、まずは気になるツールを無料で試してみましょう。
関連記事
参考情報
- AI NAVI:AI検出・チェッカーツールとは?仕組みやおすすめツールを紹介
- WORDVICE.AI:2025年:おすすめAI 判定ツール/AIチェッカー6選 (無料&有料)
- マーケティング情報局:生成aiチェッカーで判定精度と使い方を徹底比較!無料画像検出やおすすめツール最新ガイド
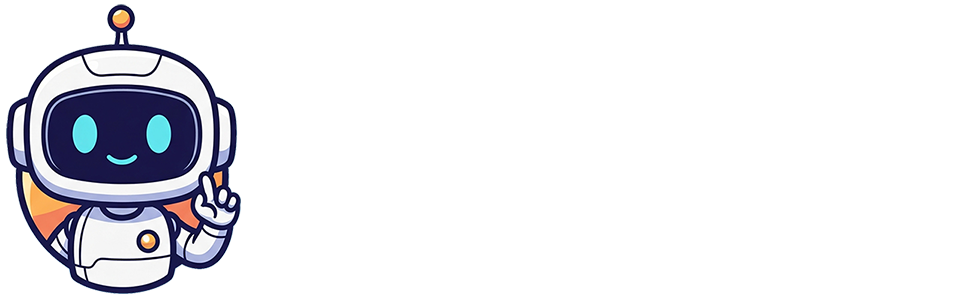
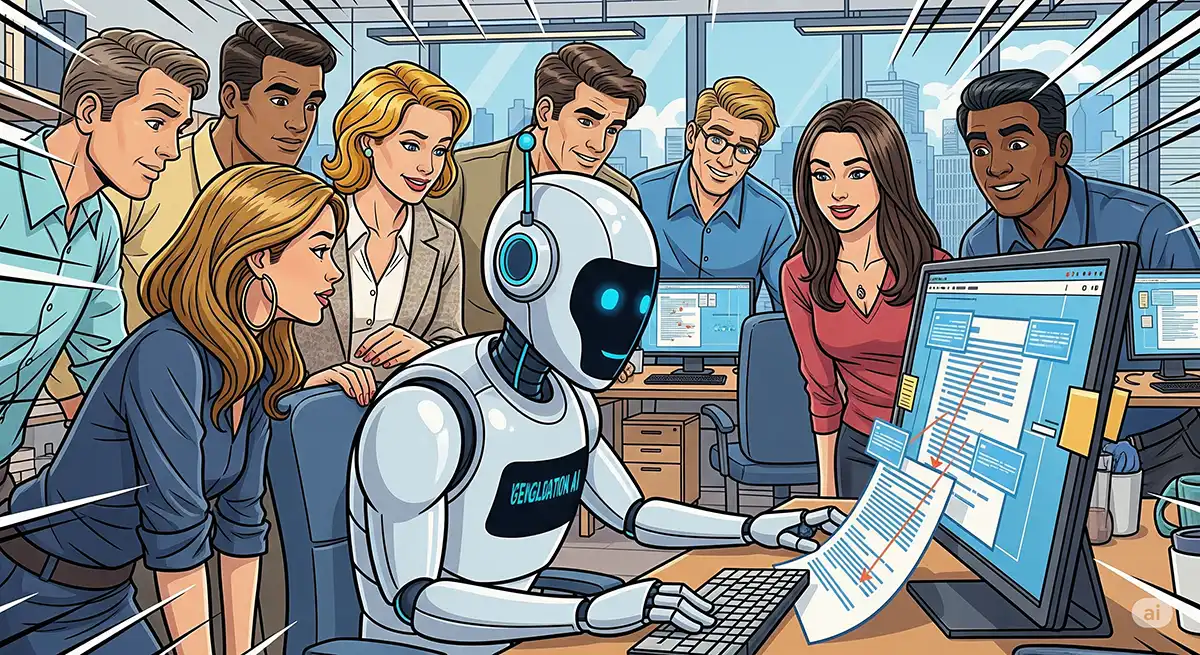


コメント